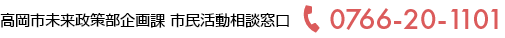夏の高岡古城公園
久しぶりの投稿となった。1か月以上投稿なしである。
夏の暑い日は外出する気になれない。富山県には「熱中症警戒アラート」が続いている。
お上の熱中症対策「不要不急の外出は避けよう」を守っていた次第である。(これは言い訳)
とは言え、やはり古城公園が気になる。
「お盆には地獄の釜も休む」と言われているが思い切って古城公園へ出かけてみた。
公園はせみ時雨
動物園でも暑さ対策。
アンパンマンが首にかけているボードには
「たいようのでている日はとてもあついです」
「とてもあついヨ さわるときけんです」
ヒョウモンガメさんの柵の上には日よけのすだれ
ネズミさん、ウサギさんのゲージの前通路には直射日光が当たらないようにシート
2023.8.16
高岡観光ボランティアガイドやまたちばな
本保澄雄
高岡城跡の新しい案内板
《やまたちばな》のインスタグラムに投稿があった通り高岡古城公園に新しい案内板が設置された。
国指定史跡で日本100名城に選定されている高岡城跡の案内板である。古城公園小竹薮駐車場から小竹薮へ上がる階段登り口左側に設置された。
高岡ロータリクラブさんがが寄贈したものしたものとか。
私はちょうどこの日公園内を散策していた。小竹薮駐車場をついたときに角田市長が式典を終えられ市役所へ帰られるところであった。
役所の担当者や新聞記者さんがおられ取材の最中であったった。
案内板には「高岡城模式図」(江戸後期)「越中高岡古城図「大図」」(江戸期)、現在図なども描かれており城跡のガイドには役立ちそうな感じ。
市の職員から案内板の設置について尋ねられ「高岡城跡後のガイドがしやすくなった」答えた。
5月31日 北日本新聞
2023.5.31
高岡観光ボランティアガイドやまたちばな
本保澄雄